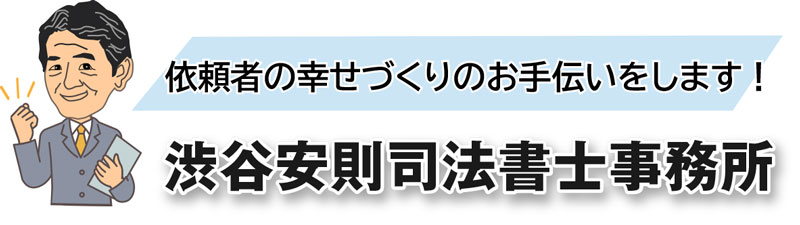商業登記 | 後見人 | 終活・遺言・事業継承 | 消費者トラブル |離婚・シングルマザー | 他人とのトラブル | 相続
後見人制度について
|
|
 |
後見人制度の例 司法書士がお役に立てること
・父が認知症になり、施設入居や貯金引き出しなどで困っている。
・将来自分が認知症になった時の不安がある。
・後見人申立ての手続きが分からない。
・将来自分が認知症になった時の不安がある。
・後見人申立ての手続きが分からない。
1 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人とは
人は、買い物をしたり住んでる家の屋根修理を頼んだり、または家を借りるなど社会生活をする上で毎日たくさんの契約をします。でもその場合に契約の結果、何が起こるかを予測できない人、あるいは予測が著しく苦手な人もいます。原因は一般的には認知症等など考えられます。知的障害も考えられます。でも契約の能力が不十分なのに契約してしまい酷い結果(例えば自宅を極安価格で売却し住む家がなくなる)になる人は守らなければなりません。他人ごとではなく、明日は我が身かも知れません。
法律行為の能力がなかったり著しく劣る人は、自分の代わりに法律行為を代理する人つまり後見人によって契約をしてもらったり、保佐人に契約をチェックしてもらうことにより社会生活を営みます。
一言でいえばそれが後見制度です。
※(被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見人)
被後見人とは 判断能力がほとんどない人。後見人が代理します。
被保佐人とは 判断能力が著しく不十分な人。保佐人が同意や代理をします。
被補助人とは 判断能力が不十分な人。補助者が同意や代理をします。
任意後見人とは 将来自分の判断能力が衰えた時に備えて、自己の能力が十分な時にあらかじめ支援する人を選んでおきます。
参照条文:民法
7条(後見開始の審判)、民法8条(成被年後見人成年後見人)、第9条(成年被後見人の法律行為)、第11条(補佐開始の審判)、第12条(被保佐人及び保佐人)、第13条(補佐人の同意を要する行為等)、第15条(補助開始の審判)、第16条(被補助人及び被補助人)
法律行為の能力がなかったり著しく劣る人は、自分の代わりに法律行為を代理する人つまり後見人によって契約をしてもらったり、保佐人に契約をチェックしてもらうことにより社会生活を営みます。
一言でいえばそれが後見制度です。
※(被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見人)
被後見人とは 判断能力がほとんどない人。後見人が代理します。
被保佐人とは 判断能力が著しく不十分な人。保佐人が同意や代理をします。
被補助人とは 判断能力が不十分な人。補助者が同意や代理をします。
任意後見人とは 将来自分の判断能力が衰えた時に備えて、自己の能力が十分な時にあらかじめ支援する人を選んでおきます。
参照条文:民法
7条(後見開始の審判)、民法8条(成被年後見人成年後見人)、第9条(成年被後見人の法律行為)、第11条(補佐開始の審判)、第12条(被保佐人及び保佐人)、第13条(補佐人の同意を要する行為等)、第15条(補助開始の審判)、第16条(被補助人及び被補助人)
2 後見人利用の具体例
(後見人制度を利用しなければいけなくなる事情の一般的事例の紹介)
事例1 認知症の父は一人で自宅に住んでいたが、父は自宅生活が困難となり施設に入所することになった。住まなくなった自宅を売却して施設入所費をねん出したいが、認知症発症の父は自宅を売却できない。
※代わりに子が父の実印を押して契約書類を作ったとしても、登記段階で必ず司法書士や登記官が止めます。
事例2 父が今年亡くなり、残された財産の整理をしたいが、母は認知症で遺産分けができない。
事例3 親は高齢者の介護施設に入所しなければ生活維持ができない。しかし入所契約を結ぼうとしたら、本人の意思確認ができない(契約できない)ので困っている。
事例4 銀行が親の認知症を知り口座凍結したので、親の生活費などが引き出せない。子である自分が生活費を立て替える等はとてもできない。
事例1 認知症の父は一人で自宅に住んでいたが、父は自宅生活が困難となり施設に入所することになった。住まなくなった自宅を売却して施設入所費をねん出したいが、認知症発症の父は自宅を売却できない。
※代わりに子が父の実印を押して契約書類を作ったとしても、登記段階で必ず司法書士や登記官が止めます。
事例2 父が今年亡くなり、残された財産の整理をしたいが、母は認知症で遺産分けができない。
事例3 親は高齢者の介護施設に入所しなければ生活維持ができない。しかし入所契約を結ぼうとしたら、本人の意思確認ができない(契約できない)ので困っている。
事例4 銀行が親の認知症を知り口座凍結したので、親の生活費などが引き出せない。子である自分が生活費を立て替える等はとてもできない。
3 後見人の申し立て
福岡近郊→福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、那珂川市、糟屋郡、宗像市、福津市
ア 自分が選んだ後見人が選任されなかったとしても、取り下げることはできません。また選ばれた後見人は本人の利益のためにのみ行動しますので、申立人の意に沿わないことはあります。
イ 必要な場合は鑑定費用が必要なことがあります。(鑑定費用は10万円前後です。)
ウ 後見が開始したらご本人が能力を回復しない限り後見はご本人がなくなるまで続きます。
エ 後見人になれない人もいます。(未成年者や破産者など)
(以上、福岡家庭裁判所ホームページ R031228_fc04_koken_seinen_kaisinomositate.pdf (courts.go.jp))
- 申立書
- 収入印紙800円分
- 収入印紙2,600円分
- 郵便切手後見:3,480円分
- 鑑定費用 医師に支払う費用です。鑑定を実施する場合のみ必要になります。 通常、上限は10万円程度。
- 診断書(成年後見制度 用)、診断書付票家庭裁判所 かかりつけの医師等に作成してもらう。
- 本人情報シートの写し、本人を日頃から支援している福祉関係者等がいる場合に作成してもらう。原本は医師に提出して,写しを裁判所に提出。
- 療育手帳、精神障害者保健 福祉手帳のコピー( 手帳をお持ちの場合にのみ)
- 戸籍謄本 本籍地役場
- 住民票 住民登録地の 市区町村役場 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。 戸籍附票(本籍地役場で発行)でも代用可能
- (後見等が)登記されて いないことの証明書 福岡法務局 郵送で申請する場合,取寄せ先が異なります。
- 申立事情説明書 家庭裁判所
- 親族関係図 家庭裁判所
- 親族の意見書
- 財産目録、相続財産目録、収支予定表 家庭裁判所
- 財産、収支の資料 家庭裁判所 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。
後見人等候補者についての書類 - 後見人候補の住民票 住民登録地の 市区町村役場 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。 戸籍附票(本籍地役場で発行)でも代用可能です。
- 後見人等候補者事情説明書 家庭裁判所
R031228_fc11_koken_seinen_shorui_tesuryoto.pdf (courts.go.jp)(書類チェック表)
R0303_s_koken_shoshiki01_moshitatesho.docx (live.com)(申立書)
上記は裁判所への提出書類ですので、自分で作成するのが大変な場合は法律専門家である司法書士等が代書し、また裁判所へ行く場合は同行もします。
後見人が選任されたら、以後は後見人が財産管理や介護契約等本人を守るためいろんなことをします。勘違いされる方もいますが本人の直接介護はしません。介護するのは介護資格を持った施設の方たちや介護の資格を有する方が行いその施設等との介護契約を成年後見人がします。※手術や終末治療等医療同意書は血縁である親族の方にお願いしてます。
後見人が選任されたら、以後は後見人が財産管理や介護契約等本人を守るためいろんなことをします。勘違いされる方もいますが本人の直接介護はしません。介護するのは介護資格を持った施設の方たちや介護の資格を有する方が行いその施設等との介護契約を成年後見人がします。※手術や終末治療等医療同意書は血縁である親族の方にお願いしてます。
4 いくらかかるか(費用)の目安です
〇 申し立て費用(裁判所印紙、郵送料、代書費用)
鑑定料 約10万円
印紙郵便代 1万円、
代書費用(司法書士に書類作成してもらう場合)約15万円~20万円
登記簿謄本費用 600円
〇 選任された後見人への報酬(本人の財産から払われます。)
基本報酬 2万円/月
管理財産額が1,000~5,000万円の場合 3万円~4万円/月
参照:令和4年2月成年後見人等の報酬額のめやす…大阪家庭裁判所
鑑定料 約10万円
印紙郵便代 1万円、
代書費用(司法書士に書類作成してもらう場合)約15万円~20万円
登記簿謄本費用 600円
〇 選任された後見人への報酬(本人の財産から払われます。)
基本報酬 2万円/月
管理財産額が1,000~5,000万円の場合 3万円~4万円/月
参照:令和4年2月成年後見人等の報酬額のめやす…大阪家庭裁判所
5 渋谷安則司法書士事務所ができるお手伝い
※ただし具体的事件ではなく単に法律勉強等のためのご質問はご遠慮ください
※相談内容が調査等に実費を要する場合や業務量が無料対応では困難になってきた場合には、予めそのことをお伝えして見積もり金額を提示します。有料となる場合は必ず見積もりを提示しますので、それをよく検討されてのちに、ご依頼をお願いしてます。
※ 鑑定料、印紙郵便代 1万円、登記簿謄本費用 当の実費は別です。